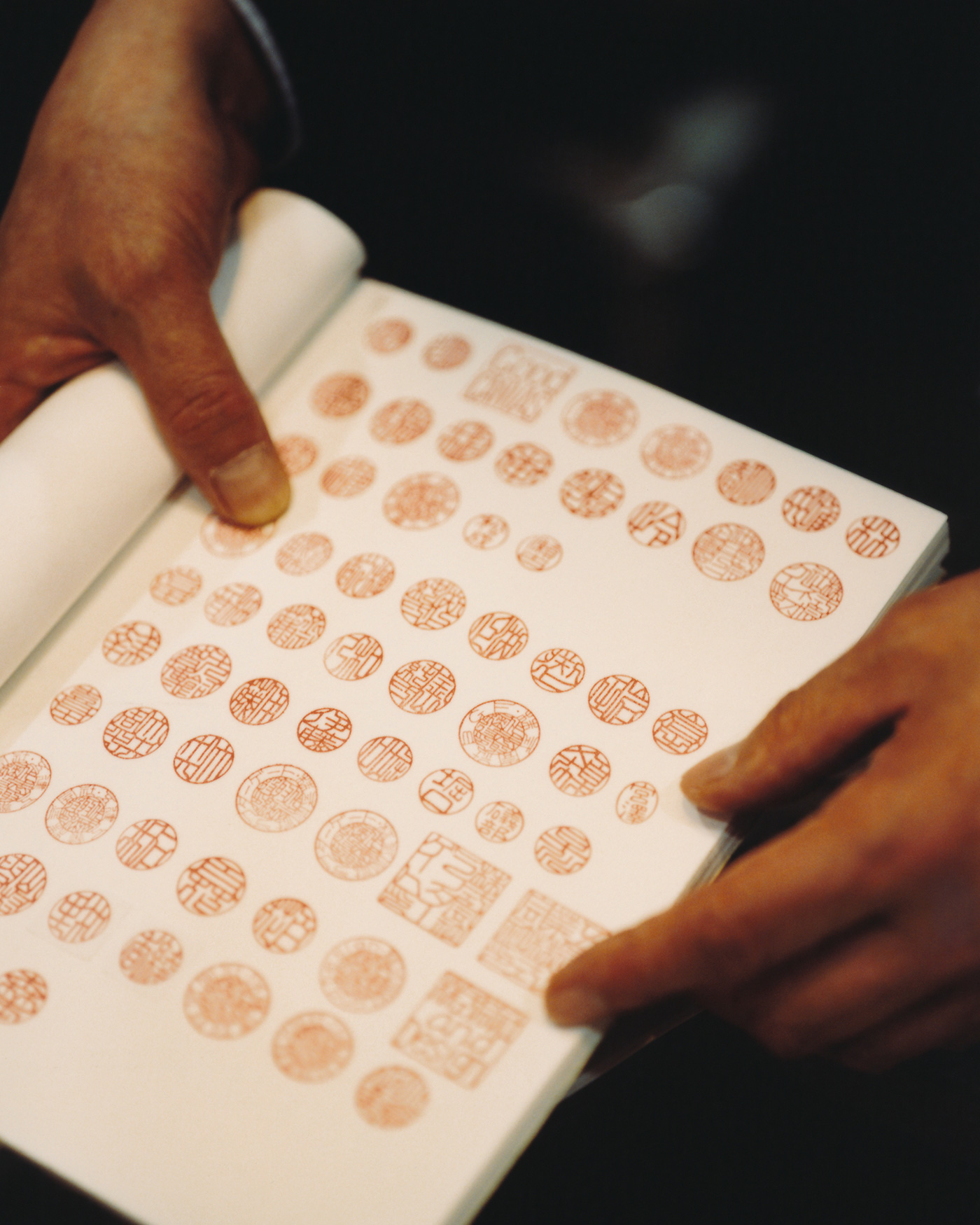今までのマル仏壇としての歴史の中で、今回のプロジェクトを通して新しいプロダクトを制作する事にはどのような意味があると思いますか。
純粋にこんなに綺麗なものなんだから、いろんな人に見てもらいたいという部分が結構大きいです。ヨーロッパに住んでいる人がどんな漆塗りを欲しいかって、僕は正直想像がつかないんですけど、そこをデザイナーさんとコラボレーションすることで、技術を変換して商品にして売ってみるっていうのは、チャレンジする価値はあると思っています。

今回デザイナーとのコラボレーションの中で、新しく取り入れた思想や、新しい技術が生まれたり、視点が変わったということはありましたか。
プロダクトの中にカラフルな燭台がありますが、これは自分たちでは絶対に考えないデザインです。こういう色の組み合わせはまず考えたこともないんですよ。日本人だからなのか、自分が職人だからなのかはわからないですけど、最初にデザインを見た時にはこれがかっこいいと思えなくて、奇抜すぎると思ったんです。今思うと、こういう配色は日本のカラーじゃないって決めつけていたんだなと思います。
実際に作られてみてどうですか。
そうですね、実際形になるとこれはこれでありなのかもなっていう感じです。今まで勇気がなかっただけなのかなって思うところもあるんですけど、まだ半信半疑ではありますね。でも、ヨーロッパの人が見て、変だって言わなかったら、こういう配色もありなんだって、それは僕たちにとってはすごい発見です。

キャンドルスタンドの素地は金属(真鍮)ですが、これには何か理由がありますか。
そう。金属なんです。何より、うちは祈りのアイテムを作る仏壇屋です。そこに漆という技術があって、それを掛け合わせたのが今回の燭台という商品です。仏具にも蝋燭立てというのがあるんですけど、それは基本的に真鍮製なんです。昔から真鍮って、錆びないし、金色でしょ。金っていうのは不浄な悪いものが寄ってこない色とされているんです。でもね、純金で全部作るとものすごい値段になっちゃうんで、その代わりとして真鍮がよく使われてきたという歴史があるんです。そういうコンセプトなので、今回の燭台は真鍮で製作しました。

今回のプロダクトを作るのに関わってる職人さんは何人くらいですか。
まず、真鍮加工屋さん。今回は鮫皮を巻く、鮫皮塗りという技法を使うので、鮫皮を提供してくれる職人さん。漆を調色してもらう漆屋さん。下地を塗る職人。それから漆を塗る職人。5人くらいですかね。
ひとつのものを作るのに、どのくらい時間がかかりますか。
燭台の大きなものは、乾燥を含めると、塗るだけで1か月かかります。漆は、乾かして塗り重ねてっていう工程があって、特に鮫皮塗りっていうのは、かなりの回数を塗らなきゃいけないんですね。具体的には鮫の皮の凹凸が埋まるくらい漆を塗らならなきゃいけない。その状態まで持っていくのにおそらく9回くらいは塗らならきゃいけない。慌てて中が乾かないうちに塗ると、仕上がりが悪いので、乾燥時間がかかりますね。

こうやって、長い時間かけて作ったものどういう人に使ってもらいたいですか。
豊かな暮らしに役立ってほしいなって思います。もっと安くて便利なものなんていくらでもあるんですけど、何を選ぶかだと思うんです。僕らがすごい手間をかけて作ったものを、評価してくれる人、綺麗って思ってもらえる人、そして買って終わりじゃなくて、生活の道具として、楽しんで使ってもらいたいです。